

家計管理をして、余剰資金でオルカンの積立をスタートして数ヶ月が経ちました。
証券口座の資産総額は増えているけど、毎月使えるお金は増えないので、日々の生活が良くなっていない。。。

高配当株投資をして配当金をもらって、毎月使える金額を増やしたいけど、
どの銘柄を選べばいいか分からないし、銘柄の調べ方も分からない。。。

高配当株投資を行いたいけど、PERとかPBRとか、EPSとかROEとか、略さないで欲しい。英字3文字がトラウマになりそう。。。

銘柄分析はできるようになったけど、購入タイミングが分からない!いつがお買い得なんですか!
確かにたくさんの銘柄があり、何を選んだら良いか難しいですね。
銘柄分析しようとしても、PERやPBRなどの専門用語は難しいですね。
でも、ポイントが分かれば、優良銘柄を選ぶことができます。
しっかり勉強して、配当金の貰える生活を送りましょう!
本記事では、私が実践する“15のチェック項目”に基づいて、安定した配当と中長期で価格が安定した日本株の選び方を丁寧にご紹介します。

貯金習慣もなかったアラフォーサラリーマンの私が、金融投資で月3万円収入を増やし、毎年家族で旅行にいくことが出来ています。
投資を上手にコツコツ行えば、誰でも月3万円収入を増やすことができますので、最後まで、そして色々な記事を読んでください。
保存版!高配当日本株の選び方〜15項目で簡単に資産形成〜
先に、結論です。
1.配当利回りのチェック(足切りライン)
①(足切り)配当利回り:3.75%以上
2.割安度(価格の割に価値があるか)
②PER:15倍未満
③PBR:0.5〜1.5倍
3.業績と財務(好業績を継続できるか)
④売上高:増加傾向
⑤EPS:増加傾向
⑥ROE:8%以上
⑦営業利益率:10%以上
⑧自己資本比率:40%〜80%
⑨BPS:増加傾向
⑩営業CF:黒字&増加傾向
⑪現金等:増加傾向
4.株主還元(配当金を継続できるか)
⑫1株あたり配当金:増加傾向
⑬配当性向:30〜50%
5.将来性と購入検討基準(将来性があるか、購入の検討を行う基準となる利回り)
⑭事業の将来性:事業の成長可能性があるか
⑮検討基準配当利回り:過去10年実績値&3年間の毎日の値から2番目に高い値
画像でまとめる以下のとおり

1項目ずつ解説したいと思います。
1.配当利回りのチェック(足切りライン)
基準① (足切り)配当利回り:3.75%以上
なぜ高配当株投資をするのでしょうか?それは配当金を得るためです。
しかも、できるだけ多くの配当金を貰いたいですよね?
そのためには、配当金を多く出している企業の株を買うことになりますが、単純に配当金額だけをみていてはダメです。
同じ配当金額であっても、株価は銘柄ごとに異なるからです。
では、次の表を見て下さい。AとBのどちらがお得でしょうか?
| 配当金額(円) | 株価(円) | ? | |
| A | 100 | 1,000 | ? |
| B | 100 | 2,000 | ? |
もちろん、株価の安いAですね!
同じ配当100円(価値)を得られるのであれば、安い値段で買う(価格)ことがお金を増やすには大事です。
価格だけでなく、価値をみて買う判断をすること!
この考え方は、色々な買物に応用できるので是非身につけていただきたいです。
さて本題に戻ります。ということでより安い価格で高い配当金を出してくれる銘柄を買うことになりますが、いちいち計算するのはめんどくさいですよね。
実は、指標として配当利回りというものが公表されています。
配当利回りとは、株価に対する年間の配当金額を言います。
計算式は、年間配当利回り (%)= 年間配当金額 ÷ 株価
つまり配当利回りが高い銘柄を選べば良いのですが、そんなに高配当株投資はそんなに優しくないのです。。。
配当利回りが高い銘柄の中には、株価が下がらないように無理して配当金を払っている銘柄があります。そのうち資金が無くなり減配や無配に転落ということもあるのです。そんな銘柄をゾンビ銘柄と言ったりします笑
配当金を目的に買ったのに、配当金が無くなったり、減ったりしたら本末転倒ですよね!
ゾンビ銘柄を避け、しっかりと配当金を貰うためにも、複数の視点(私の場合は15項目)から銘柄を分析する必要があるのです。
それでも、配当金は出来るだけ多く欲しいので、まずは配当利回りを確認することになります。
次に、どの水準からが高配当株というのでしょうか?
一般的に、配当利回り3.5%以上が高配当株と言われています。
私はもう少し欲張って3.75%以上を基準としています。
というのも、配当金には基本的に税金がかかります。税率は20.135%です。(NISA口座を除く)
税金が引かれた後に3%は欲しいので、3%÷(100-20)=3.75%を足切り基準にしています(20.135%は便宜上20%にまるめています)
ちなみに、この基準に何が正解というものはありません。
ただし、全ての上場銘柄を分析することは時間がかかりすぎますし、あまりに利回りが低い銘柄を集めても、目的の配当金が少なくなってしまいます。
ということで、
基準として配当利回りは3.75%以上!
2.割安度(価格の割に価値があるか)
基準② PER:15倍未満
次に、割安度を確認します。
割安度とは、企業の価値と株価の関係を表す指標で、株価が企業の価値に比べて低い状態であることを確認できるものです。
早速出てきましたアルファベット3文字のPER!!
私もはじめは何がなんだかわかりませんでしたが、何度も見ているうちに理解できましたので、粘り強く確認しましょう。
何かものを買う時にできれば安く買いたいですよね?
株式も同じです。
例えば、配当金が400円出る銘柄が10,000円の時に買うと、配当利回りは4%です。
一方で、配当金が同じ銘柄を20,000円の時に買うと、配当利回りは2%です。
これだったら、どの金額で買いたいですか?
もちろん10,000円の時に買いたいですよね!
同じ配当400円(価値)を得られるのであれば、安い値段で買う(価格)ことがお金を増やすためには大事です。
価格だけでなく、価値をみて買う判断をすること!
早速、2回目の登場です。この考え方は、色々な買物に応用できるので是非身につけていただきたいです。
さて、本題のPERですが、
株価収益率(Price Earnings Ratio)の略で、企業の株価が1株あたりの利益(EPS: Earnings Per Share)の何倍になっているかを示す指標です。
計算式は、PER = 株価 ÷ 1株あたり純利益(EPS)
来ましたEPS、嫌になりますね笑、でもここでは一旦無視しましょう。
次に、表を見て下さい。AとBのどちらが購入タイミングとして適切でしょうか?
| PER(倍) | EPS(円) | 株価(円) | |
| A | 10 | 100 | ? |
| B | 20 | 100 | ? |
それぞれの株価を計算すると
Aは、PER 10倍= 株価 X÷ 1株あたり純利益(EPS)100円
X=10×100なので、株価:X=1,000円
Bは、PER 20倍= 株価 X÷ 1株あたり純利益(EPS)100円
X=20×100なので、株価X=2,000円
ということで、表に入れると
| PER(倍) | EPS(円) | 株価(円) | |
| A | 10 | 100 | 1,000 |
| B | 20 | 100 | 2,000 |
どちらがお買い得でしょうか?
同じ価値(100円)が得られるのであれば、安い価格で買う方が良いので、1,000円で買った方が良いですよね。
今回の場合、2,000円の場合はPER20倍、1,000円の場合はPER10倍です。つまりPERは低い方がお買い得ということです。
では、何倍になったらお買い得と言えるのでしょうか?
スーパーで買物する時に、おなじ商品をいつも買っていると安い時期と高い時期が分かるようになりますよね。
これが正しい方法ですが、買おうと思っている銘柄の割安タイミングが分かるようになるまで見続けるのは現実的ではありません。一生買えないかもしれません。
なので、過去の経験を参考にします。
日本株の平均的なPERは15倍未満とされています。
ということで、
基準としてPERは15倍未満!
その上で、他の基準がクリアしているのに、PERだけ達成していない場合には、過去のPERや同業銘柄と比較して、割安かどうかを確認する方法が有効です。
基準③ PBR:0.5〜1.5倍
次に、割安度の確認に用いるもう一つの指標であるPBRです。
PERと同じように、ものを買うときにはできるだけ安く買いたいですよね?
PBRとは、
株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)の略で、企業の株価が1株あたりの純資産(BPS:Book-value Per Share)の何倍になっているかを示す指標です。
計算式は、PBR=株価÷1株当たりの純資産(BPS)
次にBPSが出てきましたが、これも一旦無視しましょう。
次に、表を見て下さい。AとBのどちらが購入タイミングとして適切でしょうか?
| PBR(倍) | BPS(円) | 株価(円) | |
| A | 0.5 | 1,000 | ? |
| B | 1.0 | 1,000 | ? |
それぞれの株価を計算すると
Aは、PBR 0.5倍= 株価 X÷ 1株あたり純資産(BPS)1,000円
X=0.5×1,000なので、株価:X=500円
Bは、PER 1.0倍= 株価 X÷ 1株あたり純資産(BPS)1,000円
X=1.0×1,000なので、株価:X=1,000円
ということで、表に入れると
| PBR(倍) | BPS(円) | 株価(円) | |
| A | 0.5 | 1,000 | 500 |
| B | 1.0 | 1,000 | 1,000 |
どちらがお買い得でしょうか?
PBR1.0倍は、0.5倍の時と比べて2倍の価格で買っているので、0.5倍の時に買ったほうがお買い得と言えます。
つまりPBRは低い方がお買い得ということです。
では、何倍になったらお買い得と言えるのでしょうか?
お買い得の基準は、会社が解散した時に株式を購入した価格が返金されることを根拠に設定しています。
会社が倒産した場合に資産は分配されます。PBRが1.0倍の時に購入した銘柄は、購入金額=1株あたり純資産なので、買った瞬間に解散した場合、理論上は買った価格が返金されることになります。
もちろん、現実はそこまできれいには行きませんが、高値で買わうことは避けられます。
つまり、PBRが低い方が解散した時に受け取れる金額よりも安く買えるということになるので、割安といえます。PBR0.5倍は、買った時点で1,000円の価値のものを500円で買えたので、価格よりも価値が高いといえますね。
なぜ、PBRは0.5~1.5倍としているのでしょうか?
日本の多くの業種でその基準の範囲(PBR=0.5~1.5倍)におさまっている場合が多いためです。
安定して配当を受け取るためには、業績も安定していることが重要ですので、特別な値となっている銘柄ではなく、安定した値となっている銘柄を選ぶことが重要です。
ということで、
基準としてPBRは0.5〜1.5倍!
3.業績と財務(好業績を継続できるか)
基準④ 売上高:増加傾向
次に、業績と財務を確認します。
業績と財務では、企業が好業績を継続できるかを確認します。
まずは、売上高です。
売上高とは企業が商品などを販売して得た金額の合計です。
配当金は企業の利益から支払われますので、利益の源泉である売上高が増加していることが大事です。
ということで、
基準として、売上高は増加傾向!
基準⑤ EPS:増加傾向
次に、EPSです。
再度の登場のEPSです。多くの方が苦手なアルファベット3文字シリーズですが、諦めずに学びましょう!
EPSとは、Earnings Per Shareの略です。1株当たり純利益を示す指標で、企業の稼ぐ力を示します。
計算式は、EPS = 当期純利益 ÷ 発行済株式数
配当金は企業の利益から支払われます。安定した配当金を出し続けるには、利益が毎年増加していくことが大事です。
配当金は1株単位に支払われますので、1株あたりで利益が増加していることが、配当金の安定、更には増加につながります。
ということで、EPSが増加していることを基準としています。
基準として、EPSは増加傾向!
基準⑥ ROE:8%以上
またまた、アルファベット3文字です。
ROEとは、Return On Equityの略です。企業の自己資本(株主が出資したお金)に対して、どれだけの利益を上げているかを示す指標で、企業の稼ぐ力の効率性を測るものです。
計算式は、ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100
基準はどのように設定したかというと、
日本企業の平均ROEはおよそ6~8%であり、それを上回れば、配当金がしっかりと貰える可能性が高いと考え、ROEは8%以上としています。
基準として、ROE:8%以上!
基準⑦ 営業利益率:10%以上
ようやく日本語ですね笑
営業利益率とは、売上高に対する営業利益の割合を示す指標で、企業の本業での稼ぐ力の効率性を測るものです。
本業から利益を出せているか?を企業全体からみる指標です。
計算式は、営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
基準はどのように設定するかというと、
配当金は企業の利益から支払われますので、利益を効率的に出した方が良いですし、特に本業での利益が大きいことは継続的に配当金を出すためにも重要です。
では、10%という数値はどのような意味を持つのかというと、
日本の上場企業の営業利益率の平均は5~8%程度とされており、10%を超える企業は全体の約30~40%に入る傾向があります。
平均を上回る企業を選ぶことができるため、10%以上を基準としています。
基準として、営業利益率:10%以上!
基準⑧ 自己資本比率:40%〜80%
自己資本比率とは、企業の総資本のうち、自己資本(純資産)が占める割合を示す指標で、企業全体の財務状況の健全性を示す指標です。
計算式は、自己資本比率(%) = (自己資本 ÷ 総資本) × 100
自己資本比率が高いほど、返済義務のある負債(他人資本)に依存していないため、財務状況が安定しているといえます。つまり倒産しにくいということです。
倒産されると配当金が貰えないので困ります。
では基準として示している40~80%という数値はどのような意味を持つのかというと
40%未満の場合、他人の資本に依存しているため、経済危機や金利上昇局面で倒産リスクや減配リスクが高まります。
一方で、80%を超える場合には、収益が成長投資や株主還元に使われていない可能性があり、今後の業績不振や増配されない可能性が生じます。
倒産しにくく、増配の可能性があり、今後の成長が期待でき、株主還元をしっかり行っている企業を選ぶため、自己資本比率は40%〜80%を基準としています。
基準として、自己資本比率:40%〜80%!
基準⑧ BPS:増加傾向
BPSとは、「Book-value Per Share」の略です。1株あたり純資産を示す指標で、企業の財務状況の健全性を示す指標です。
計算式は、BPS = 純資産 ÷ 発行済株式数
BPSが高くなるほど、解散した時に株主に帰ってくる金額が多くなります。
BPSが増加傾向である銘柄を買うことで、もしも数年後解散してしまった場合にも、購入価格よりも大きい金額が返ってくる可能性が高まることになります。
ということで、BPSは増加傾向であることを基準としています。
基準として、BPS:増加傾向!
基準⑩ 営業CF:黒字&増加傾向
営業CFとは、営業キャッシュフローと読み、本業の現金収入と支出の差額を示す指標です。企業の稼ぐ力を確認できます。
プラスであれば本業で利益をあげられ資金が増えていることが分かり、マイナスであれば本業で利益があげられていないため、資金が減っていることが分かります。
企業の利益があがっていかないと配当金はもらえないので、営業CFは黒字(プラス)かつ増加傾向であることを基準としています。
基準として、営業CF:黒字&増加傾向!
基準⑪ 現金等:増加傾向
現金等とは、現金及び現金同等物を表します。具体的には、手元にある現金、預金、そして満期日が3ヶ月以内の短期的な投資などを指します。
現金が少ない場合、材料などの仕入れ、新しい設備投資、給料などの支払いが出来なくなります。つまり企業としての活動が制限されることにつながります。
企業が安定した成果を出してもらわないと、安定した配当はもらえませんので、現金等は増加傾向であることを基準としています。
基準として、現金等:増加傾向!
4.株主還元(配当金を継続できるか)
基準⑫ 1株あたり配当金:増加傾向
次に、株主還元を確認します。
株主還元では、企業が配当金を継続的に出し続けられるかを確認します。
まずは、1株あたり配当金です。
配当金とは、企業が株主に利益を現金で分配することです。高配当株投資の場合これをもらうことが目的になりますね。
何度も出てきていますが配当金は企業の利益から出ています。つまり業績が悪く利益が上がらない場合には配当金が無くなることもあるのです。
これまでの指標でも業績等の確認はしていますが、いくら業績がよくても配当金がなくては高配当株投資をしている意味がありません。つまり配当金の確認は必要です。
高配当株投資では購入した時の配当金額がもらえれば良いという考え方になりますが、企業の業績で配当金が下がること(減配)を可能な限り避けたいので、配当金は上昇傾向であることを基準としています。
基準として、1株あたり配当金:増加傾向!
基準⑬ 配当性向:30〜50%
配当性向とは、企業の利益のうち、どれだけを配当金として株主に支払っているかの割合を示す指標です。
計算式は、配当性向(%)=(配当金支払総額 ÷ 当期純利益)× 100
または、配当性向(%)=(1株当たり配当額 ÷ 1株当たり当期純利益)× 100
配当性向が高すぎると、たくさん配当金を出して嬉しいけど、業績が少しでも悪化すると減配せざるを得ない状況になってしまいますし、現金が減るので将来の成長に投資できなくなってしまいます。
一方で低すぎる場合は、配当金を払わない企業となるので、今後の増配の可能性も下がるし、業績悪化時に減配する可能性が高いといえます。
また、日本企業の平均的な配当性向は約30~40%であり、株主への利益還元と将来への事業投資のバランスが優れている数値として定着しています。
さらに、配当を株主還元策として重視している企業では、配当性向を50%としているところもあります。
平均を基準にしつつ、株主還元を重視する企業も対象にするために、配当性向は30〜50%としています。
基準として、配当性向:30〜50%!
5.将来性と購入検討基準(将来性があるか・購入を検討する基準の利回り)
基準⑭ 事業の将来性:事業の成長可能性があるか
最後に、将来性と購入検討基準です。
将来性では、企業の事業の成長可能性を確認します。
まずは、将来性です。
これまでは、現在の事業の状況を確認してきましたが、未来のことをしっかりと考えて、実施しているかどうかも大事です。
新たな事業や事業の改善をしていかないと、将来的には売上が下がってしまいます。
具体的には何を見たら良いかというと、各社のIR情報から、中期経営計画や決算説明資料を確認し、事業内容事に将来性があるかどうか、その程度を確認します。
例えば、以下のような内容を確認します。
- 新たな事業モデルに投資しているか?
- 人口増加をターゲットにした事業をおこなっているか?
- ESG投資など環境に配慮した取り組みにつながる事業をおこなっているか?
ざっくり言うと、社会課題の解決に向けた取り組みをしているかと言えるかなと思っています。
業種や会社ごとに特色がありますので、色々と見ていくと面白いですよ。
基準⑮ 検討基準配当利回り:過去10年実績値&3年間の毎日の値から2番目に高い値
最後に、検討基準配当利回りです。
基準①で配当利回りの足切りはして、基準②のPERと基準③のPBRで割安度を確認するものの、銘柄毎に配当利回りの幅は異なります。
また、割安度を確認するPERやPBRは、配当金に直接連動していないので、配当利回り自体が低いタイミングになっていないかどうかを判断することは難しいので、検討基準配当利回りを設けています。
具体的にどのように基準を設定しているかと言うと、
過去10年間の利回り実績の値と、過去3年間の毎日の利回りの値の両方を比較して2番目に高い値を概ねの基準として設定しています。
なるべく利回りが高く、株価が安いタイミングで仕込めると良いですね。
基準として、検討基準配当利回り:過去10年間の利回り実績の値と、過去3年間の毎日の利回りの値の両方を比較して2番目に高い値!
6.確認ツール
これまでの数値などをどのように確認すれば良いのか、知らない方もいらっしゃると思いますので、ご紹介します。
ツール① Yahoo!ファイナンスなど
以下の基準は、Yahoo!ファイナンスなどのサイトで確認できます。
- 基準①(足切り)配当利回り:3.75%以上
- 基準②PER:15倍未満
- 基準③PBR:0.5〜1.5倍
ツール② IR BANK
以下の基準は、IR BANKのサイトで確認できます。
また、決算短信の最新情報は、各社ホームページのIRページで確認できます。
業績と財務、株主還元について確認出来ます。
- 基準④売上高:増加傾向
- 基準⑤EPS:増加傾向
- 基準⑥ROE:8%以上
- 基準⑦営業利益率:10%以上
- 基準⑧自己資本比率:40%〜80%
- 基準⑨BPS:増加傾向
- 基準⑩営業CF:黒字&増加傾向
- 基準⑪現金等:増加傾向
- 基準⑫1株あたり配当金:増加傾向
- 基準⑬配当性向:30〜50%
ツール④ 各社ホームページのIRページ
以下の基準は、各社ホームページのIRページで確認できます。
事業の将来性について確認出来ます。
- 基準⑭事業の将来性:事業の成長可能性があるか
ツール⑤ IR BANK、バフェット・コード
以下の基準は、IR BANK、バフェット・コードのサイトで確認できます。
検討基準配当利回りを決めます。
- 基準⑮検討基準配当利回り:過去10年実績値&3年間の毎日の値から2番目に高い値
過去10年実績値はIR BANKで確認できます。
&3年間の毎日の値から2番目に高い値は、バフェット・コードで確認できます。
どのツールも無料で活用できます。本当にありがたいです。
どの場所を見ればよいのかは、別途紹介します。
結論 保存版!高配当日本株の選び方〜15項目で簡単に資産形成〜
以上をまとめると、日本株の高配当銘柄の選び方は、以下のとおりです。
1.配当利回りのチェック(足切りライン)
①(足切り)配当利回り:3.75%以上
2.割安度(価格の割に価値があるか)
②PER:15倍未満
③PBR:0.5〜1.5倍
3.業績と財務(好業績を継続できるか)
④売上高:増加傾向
⑤EPS:増加傾向
⑥ROE:8%以上
⑦営業利益率:10%以上
⑧自己資本比率:40%〜80%
⑨BPS:増加傾向
⑩営業CF:黒字&増加傾向
⑪現金等:増加傾向
4.株主還元(配当金を継続できるか)
⑫1株あたり配当金:増加傾向
⑬配当性向:30〜50%
5.将来性と購入検討基準(将来性があるか、購入の検討を行う基準となる利回り)
⑭事業の将来性:事業の成長可能性があるか
⑮検討基準配当利回り:過去10年実績値&3年間の毎日の値から2番目に高い値
画像でまとめる以下のとおり

項目は多いですが、何度も見ることで理解できるようになってくると思いますので、頑張りましょう!
以下は注意点です。
15年以上の長期投資をすることが大切です。
また、一気に購入することは一切オススメしません。
購入することについては自己判断になります。
さらに投資をする前には、必ず家計管理をして投資に充てられる資金の見える化と確保しましょう。
た、金融投資をするためには証券口座が必要です。
オススメの証券口座は
- SBI証券
- 楽天証券
また、お金のことを学びたい方に、オススメの本はこちら!
【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学

しっかりと勉強して、高配当株を実践し、お金を増やして、お金を増やすこと以外にも時間を使えるようになりましょう!
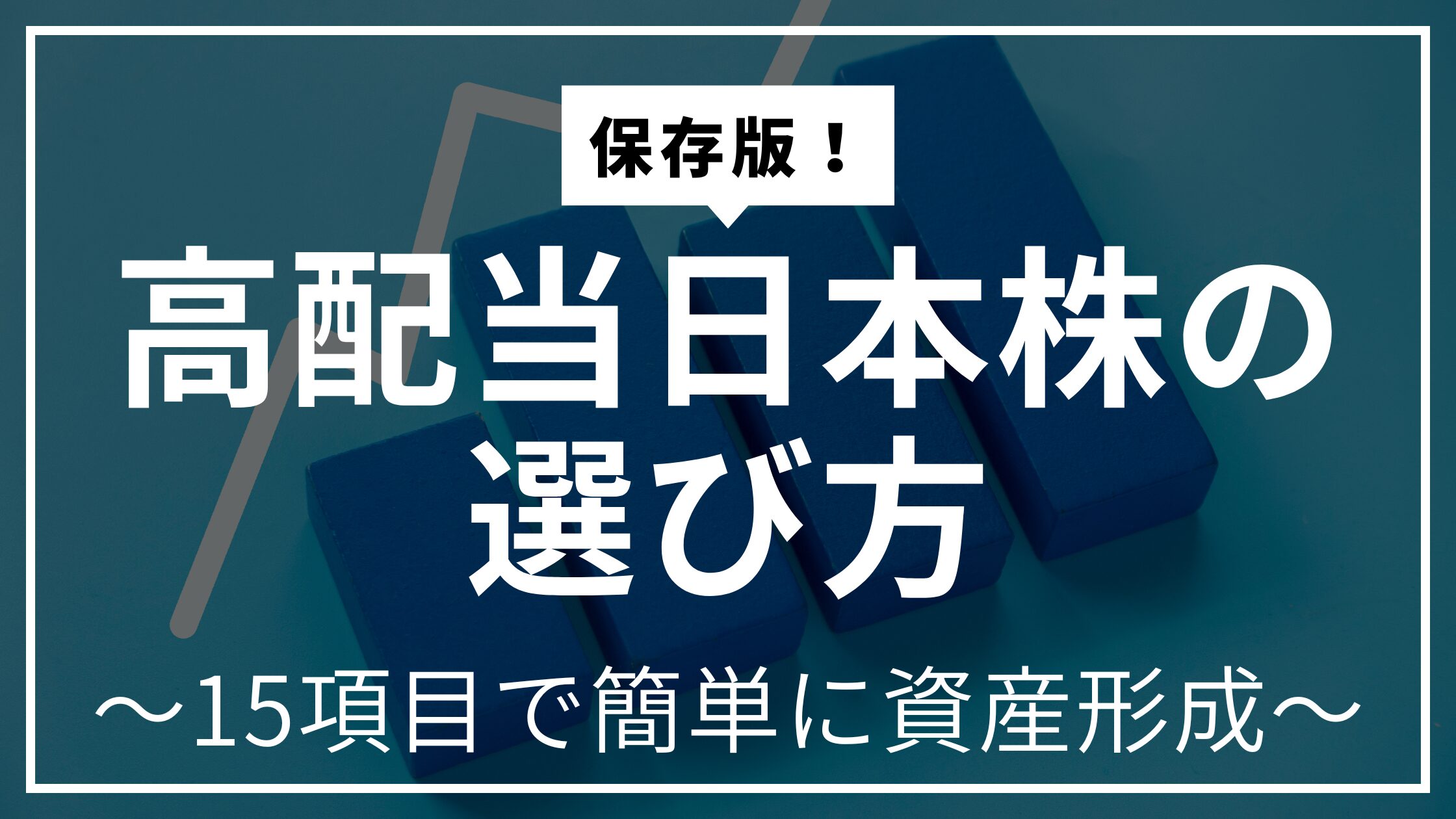
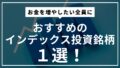
コメント